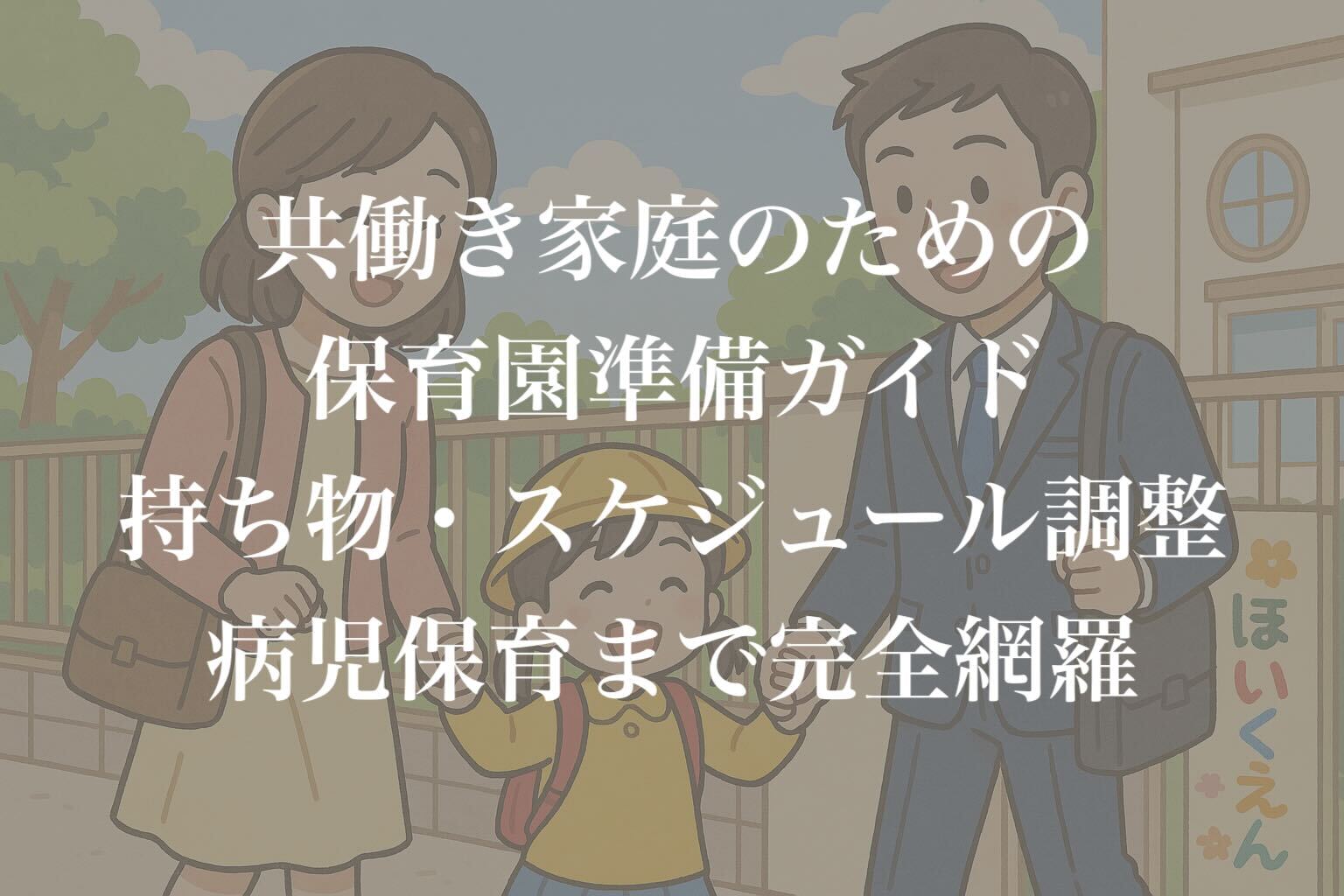保育園の入園が決まると、ワクワクする一方で
・何を準備すればいいの?
・共働きだけどスケジュールはどうしよう?
・風邪をひいたりしたらそうしたらいいのかな?
など、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
特に共働き家庭の場合、仕事と育児の両立をスムーズに進めるために、事前準備が重要です。
この記事では、共働き家庭が保育園入園までにやっておくべき7つのことを詳しく解説します。
目次
1. 慣らし保育期間のスケジュール調整
慣らし保育とは?
慣らし保育とは、子どもが保育園に徐々に慣れていくために、短時間からスタートして少しずつ時間を延ばしていく期間のことです。
【慣らし保育のスケジュール例】
| 1日-3日目 | 初日は1時間。2,3日目は1時間半~2時間 |
| 4日-6日目 | 午前~給食まで |
| 7日-8日目 | 午前~お昼寝まで |
| 9日-10日目 | 午前~おやつまで |
| 11日目以降 | 通常保育 |
多くの保育園では、1〜2週間かけて行いますが、園によっては1ヶ月ほどかける場合もあります。
入園の年齢によっても異なるので園に確認してみてくださいね。
スケジュール調整のポイント
慣らし保育は1~2週間ほどかかるため、仕事開始のタイミングなど調整するべきポイントがいくつかあります。
・会社に相談し、慣らし保育期間の休みや時短勤務を調整する
・休みが取れない場合は、祖父母やファミリーサポート、ベビーシッターの活用を検討する
・慣らし保育の期間がどのくらい必要か、保育園に事前確認する
・仕事復帰のスケジュールを考慮し、無理のないスケジュールを組む
・急な体調不良に備え、職場と柔軟に対応できる体制を整える
慣らし保育の期間は、子どもの性格や体調にも左右されるので、なかなか思うように慣らし保育が進まないこともあります。
でも、焦らずお子さんのペースに合わせて進めてあげてくださいね。

2. 送り迎えの役割分担を決める
送り迎えは夫婦で分担を!
共働きの場合、送り迎えをどちらが担当するか事前に決めておくとスムーズです。
特に、仕事の都合や通勤ルートを考慮し、無理のない範囲で調整しましょう。
具体的な決め方
つづいて、具体的な決め方を紹介します。
- 勤務時間と通勤時間を考慮する
・例えば「朝はパパ、帰りはママ」という形もアリ
・出勤時間が早い方が朝の送りを担当するなど、合理的な分担を - 急な残業や出張がある場合の対応を決める
・仕事の状況に応じて、シフト制で柔軟に対応できるとベスト
・両親やシッターのサポートを事前に依頼できるよう準備する - 延長保育の利用可否を確認する
・延長保育がある保育園なら、利用時間や料金を事前にチェック
・送迎時間に遅れそうな場合の対策も考えておく

また、夫婦間だけでなく、近くに住む祖父母やベビーシッターサービスを活用するのも有効です。
事前に準備しておけば、いざというときに安心できます。
以下の記事でベビーシッターサービスについて紹介しているので、興味のある方はぜひ参考にしてください。
3. 職場への報告とスケジュール調整
職場に報告するタイミング
保育園入園が決まったら、早めに上司や同僚に報告しましょう。
特に、慣らし保育の期間や、子どもの体調不良による急な休みの可能性を伝えておくと、職場側も対応しやすくなります。
報告時のポイント
- 慣らし保育のスケジュールを伝え、休みや時短勤務の相談をする
- 突発的な欠勤が発生する可能性があることを理解してもらう
- 周囲に迷惑をかけないよう、業務の引き継ぎを考えておく
- フレックスタイム制や在宅勤務の活用を検討する
- 職場の子育て支援制度(育児休業や時短勤務)を確認する
会社によっては、子育て支援制度が充実している場合もあります。
制度を活用しながら、無理のない範囲で仕事と育児を両立できるようにしましょう。
4. 保育園準備グッズの事前購入
保育園入園にあたり、準備するものがたくさんあります。
名前つけは意外と時間がかかるので、早めに準備しましょう。
0歳児については以下の記事でも紹介しているので、0歳児ママさんは参考にしてみてください。
必要な持ち物リスト
保育園によって異なりますが、基本的には以下のようなものが必要になります。
・通園バッグやリュック
・お昼寝用布団(保育園によっては不要)
・お昼寝用シーツ、ブランケット
・着替え(上下2~3セット)
・食事用エプロン(複数枚用意)
・タオル(お手拭き・口拭き)
・おむつ、おしりふき(必要枚数を事前確認)
・コップ・歯ブラシセット(必要な場合)
・ビニール袋(汚れた服を入れるため)
月例によって持ち物は変わってくるので、こちらも園に確認しましょう。
おすすめアイテム紹介
我が家やこれまで使ってきた商品を一部紹介していきます。
おすすめ:コットカバー
我が家はコットカバーが必要なのですが、こちらをずっと使っています。
厚さが寝心地も良さそうで、表面が毛玉になったりもしないので長くきれいに使えています。
裏地がメッシュなので夏でも通気性が良い点もポイントです◎

おすすめ:ブランケット
ブランケットは夏用と冬用でそれぞれ分けています。
息子がキャラクターに興味をもつようになってから、夏用はキャラクターブランケットになりました。
どれも何度も洗濯していますが、へたらずちゃんと使えています。
おすすめ:歯ブラシ
歯ブラシは年少クラスになって持っていくようになりました。
こちらを買ってストックしてあります。
柄も色々あるので、好きなのを選んでもらうと子供も歯磨き意欲がアップしそうですね。

おすすめ:通園リュック
リュックは成長過程で色々変えているのですが、使っていたものを紹介します。
肩がどんどんズレて来ちゃうので、前のバックルやマジックテープがあるのがポイントです。
色展開が多いので子供のモチベーションアップのために選んでもらうのもいいですね。
おすすめ:名前つけアイテム
意外と面倒な名前つけは、シールやスタンプを利用すると時短になりおすすめです。
以前洋服や靴下も名前シールではなくスタンプを使用していたのですが、シールがめっちゃ楽です!
しかも案外取れないので洗濯しても全然大丈夫です◎
準備のポイント
- 必要なものは早めに購入し、名前つけをしておく
- 汚れやすいものは洗い替え用に多めに用意する
- 園によって指定がある場合があるので、入園説明会で確認する
- 高価なものではなく、洗いやすく使いやすいものを選ぶ
特に名前つけは意外と時間がかかるので、早めに取り掛かるのがおすすめです。
ぜひ先ほど紹介したアイテムなどを活用してみてくださいね♪
5. 病児・病後児保育の登録をしておく
病児・病後児保育とは?
子どもが急に熱を出したとき、保育園では預かってもらえません。
そんなときのために、病児保育(病気中でも預かり可能な施設)や病後児保育(回復期の子どもを預かる施設)に登録しておくと安心です。
病児・病後児保育登録の流れ
病児・病後児保育施設の一般的な利用の流れや持ち物、料金を説明します。
簡単な流れ
- 事前に各施設にて利用登録
- お子さんが発熱、発病
- 施設への連絡(予約)&病院受診
- 病児・病後児保育施設へ入室
必要なモノ
- 保険証、乳幼児医療証
- 母子手帳
- お薬、お薬手帳
- 着替え
- おむつや下着
- ミルクや食事(持ち込み不要な場合もあり)
- ビニール袋
いざという時のために、事前に登録しておくと安心です。
自治体によって流れや持ち物が異なるので、ご自身の地域サイトなどを確認してみてください。
料金は大体1日2,000円~3,000円前後が相場なようです。
6. 子どもの生活リズムを保育園仕様にする
保育園の1日のスケジュールを把握する
保育園の生活リズムは、自宅とは異なることが多いため、入園前に少しずつ慣れさせていくのがおすすめです。
【保育園のスケジュール例】
| 時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 7:30 ~ 9:00 | 登園・自由遊び |
| 9:00 ~ 9:30 | 朝の会・挨拶・体操 |
| 9:30 ~ 10:00 | おやつ(幼児はなし) |
| 10:00 ~ 11:30 | 主活動(制作・戸外遊びなど) |
| 11:30 ~ 12:30 | 昼食 |
| 12:30 ~ 15:00 | お昼寝 |
| 15:00 ~ 15:30 | おやつ |
| 15:30 ~ 16:30 | 自由遊び・設定保育 |
| 16:30 ~ 18:30 | 降園・延長保育 |
最初はうまくいかないかもしれませんが、少しずつ慣れていきます。
焦らずママやお子さんのペースで進めていきましょう。
生活リズム調整のポイント
全てを保育園の通りに過ごす必要はありません。
特に大事なポイントは、
✅朝は決まった時間に起きる
✅ごはん(ミルク)を食べる
✅夜更かししない
という3点です。
ちゃんとお昼寝できるかな?
決まった時間にご飯食べた方がいいかな?
など不安になると思いますが、子供はすぐに慣れてきます😊
何より規則正しく起きて、食べて、寝られればOKです!
共働きだと朝も夜もバタバタしてしまいますが、ぜひこの3点だけ意識して生活してみてください。
7. 子どもに「保育園に行くよ」と伝え始める
子どもに安心感を与える
初めての環境に不安を感じる子どもも多いので、少しずつ「保育園って楽しいよ」と伝えていきましょう。
具体的な方法
お話だけでは子供にはなかなか伝わりづらいかもしれません。
具体的な方法をいくつか紹介します。
- 保育園に関する絵本を読み聞かせる
- アニメなど動画を一緒に見てみる
- 園の近くを散歩し、「ここが保育園だよ」と教える
- 「先生とお友達がたくさんいるよ」と楽しいイメージを伝える
日常に保育園を取り入れ、少しでもお子さんのイメージが膨らむようにできるといいですね。

年少という事もあって早々に理解していたので、意外とスムーズに入園できました。
まとめ|入園準備は早めに計画的に進めよう
共働き家庭にとって、保育園入園は大きなライフイベントです。
スムーズに仕事と育児を両立するために、以下の7つの準備を進めておきましょう。
- 慣らし保育期間のスケジュール調整
- 送り迎えの役割分担を決める
- 職場への報告とスケジュール調整
- 保育園準備グッズの事前購入
- 病児・病後児保育の登録をしておく
- 子どもの生活リズムを保育園仕様にする
- 子どもに「保育園に行くよ」と伝え始める
早めに準備を進めることで、不安を減らし、安心して新生活をスタートできます。
共働き家庭の皆さんがスムーズに保育園生活を迎えられるよう、ぜひ参考にしてください!